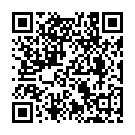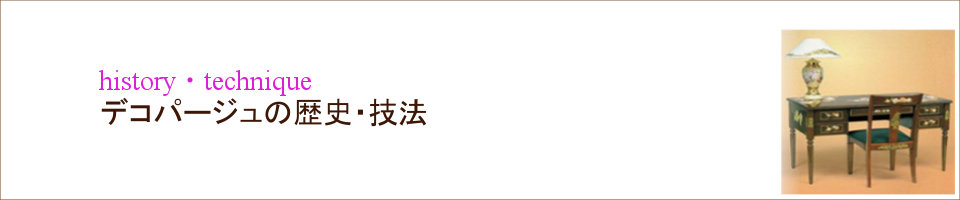
デコパージュとはフランス語でdecouper(切る・切り取る)を語源とする言葉で、好みのプリント絵画を
切りぬき、木板(プラーク)や宝石箱・家具、陶器、布、皮、金属、ガラス、プラスチック等に貼って装飾し、その上に何度もデコパージュ用の透明の仕上げ剤を塗り重ねていきます。美しい工芸品を作りあげる
手工芸です。
デコパージュは、16世紀に、日本のうるし塗りの漆器に憧れたイタリアの家具職人が始めたもので、白黒の
プリントにカラーを手塗りして家具に装飾をしました。その後18世紀には、フランス宮殿を中心とした上流
階級で流行し、ヨーロッパ中に広まりました。
19世記には、アメリカに渡り、デコパージュ用の塗料やアートプリントの開発に伴い、誰でも楽しめるよう
になり、60年代から大流行しました。
日本では、70年代より上陸し手工芸の一分野になりました。
色々な技法があり、プリントを使用しますので、絵心のない人、誰にでも楽しくできる手工芸です。
![]() 基本作業
基本作業
木板(プラーク)に色を付ける時は木目にそってサンドペーパーをかけます。木地が悪い場合は、ジェッソ(下塗り剤)を塗った後、さらにサンドペーパーをかけます。好みの色を塗りよく乾燥させます。2~3回塗ります。プリントを貼ります。仕上剤を10位塗ります。平らにするために耐水ペーパーでみがき、また仕上げ材を塗ります。(それを2~3回位繰り返します。)
家具・木板(プラーク)等、木目を生かした着色をする時は、サンドペーパーは木目を傷つけないようにします。オイルステインは布に少しとり、木目にそってすりこみます。良く乾かさないと貼ったプリントににじみでるので、貼る物に最初に1~2回位仕上剤を塗ってから貼るとよいです。家具は10回塗っては耐水ペーパーをかけ、塗っては耐水ペーパーをかけ、50回以上は塗り表面が平らにるぐらい塗り、最後にワックスを塗ります。
![]() 3-D(シャドーボックス)
3-D(シャドーボックス)
同じプリントを数枚用意し、シーラー(プリント保護剤)を塗ります。プリントをカットし自然の凹凸を付けシリコン等を使って重ねて貼る。仕上剤を塗り深い額に入れます。
![]() ルプゼ(丸みのある立体感を出す)
ルプゼ(丸みのある立体感を出す)
プリント2枚にシーラー(プリント保護剤)を塗ります。1枚を木板(プラーク)等に貼り、もう1枚のプリントは、ふくらませたい部分をカットします。
貼ったプリントのふくらませたい部分にグルー(デコパージュ専用のり)を塗り、粘土をのせて
カットしたプリントを重ね合わせて周囲をおさえて、絵に表情をつけます。
貼った周りが目立つ場合は同色で色を付ける。仕上剤をぬります。
![]() トランスファールプゼ(プリントをフィルム状にし丸みのある立体感を出す)
トランスファールプゼ(プリントをフィルム状にし丸みのある立体感を出す)
プリントにマジックアート(プリントをフィルム状にする)を6~7回塗り、時間をおいてから、水で柔らかくして、裏紙をはがします。フィルム状にしたプリントをカットします、花瓶などにグルー(デコパージュ専用のり)を塗り、粘土をのせ、カットしたフィルム状プリントを貼り形をつけて、仕上げ剤を塗ります。
☆ポイント☆プリントが1枚しかない場合・ガラス・バック・ブローチ等を作る時にこの技法をつかいます。
![]() クッキーカッター(シャープな立体感を出す)
クッキーカッター(シャープな立体感を出す)
同じプリントを数枚用意します。1枚は木板(プラーク)に貼ります。
1枚はクッキーカッターにする部分だけを細かくカットします。
部分カットしたものの裏に、平らに粘土を置き、プラークにグルーを塗り
カットしたプリントをのせて、その後、丸みや線を押さえ、形をととのえます。
全部貼り終え、充分乾燥してから、粘土の側面を着色し、
仕上剤を塗ってしあげます。
携帯からご覧の場合は
下記のQRコードで